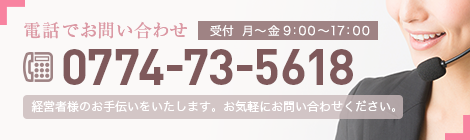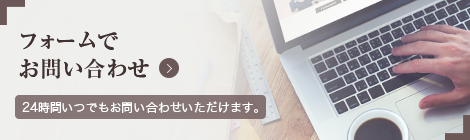No.762025.1.1
令和7年度 税制改正大綱 公表
(令和7年1月1日更新)
給与所得控除の引上げ等を含む主な内容が、令和7年度税制改正の主要項目および今後の税制改正にあたっての基本的考え方として示されているので紹介します。
◎物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応
→ 所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58万円に引き上げる。
→ 給与所得控除については、最低保障額を55万円から65万円に引き上げる。
→ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が
特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を
超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。
→ 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円と
する。
→ 以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する。
→ 個人住民税については、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設ならびに扶養親
族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとし、令和8年度分の個人
住民税から適用する
→ 自動車通勤を行う者への通勤手当については、非課税限度額を定めてきた人事院による新たな調査が行われ
る際には、その結果に基づき、迅速に見直しを行う。
◎私的年金等に関する公平な税制のあり方
→ 確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う。
→ 個人事業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引上げを行う。
→ 確定拠出年金の拠出限度額の考え方について、次期年金制度改革までに検討し、結論を得る。
→ 退職金や私的年金等のあり方は、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担を確保できる包
括的な見直しが求められる。例えば、各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員それぞれに私的年金等を管
理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全体像の共有を深め、具
体的な案の検討を進めていく。
◎公的年金等に関する公平な税制のあり方
→ 公的年金について、在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、給与所得控除と公的年金等控除の合計
額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和8年度税制改正におい
て法制化を行う。
◎人的控除をはじめとする各種控除の見直し
→ 高校生年代の扶養控除およびひとり親控除については、令和8年分の所得税および令和9年度分の個人住民
税は現行制度を維持し、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を
得る。
◎子育て支援に関する政策税制
→ 以下については、令和7年限りの措置として講ずる。
・子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充.
・子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充.
・子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充.
→ 所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から控除し、個人住民税の減収額は、全
額国費で補填する。